
詳解 確率ロボティクス Pythonによる基礎アルゴリズムの実装 (KS理工学専門書)
- 作者:上田隆一
- 発売日: 2019/12/20
- メディア: Kindle版
目次
はじめに
前回の記事では、
センサ値の度数分布を可視化して、
平均値や分散、標準偏差を計算
するJuliaコードを紹介しました。
それに続いて今回は、
各センサ値の頻度から確率分布を
計算し、そこから確率モデルを導出、
可視化するJuliaコードについて
紹介します。
GitHubリポジトリ
本記事で紹介するJuliaコードは全てこちらの
リポジトリにて公開しています。
頻度の集計
次のようなセンサ値のリストから
各センサ値の出やすさ(確率)を数値化
することで、回目以降に
観測されるセンサ値がどうなるかを
予測することができます。
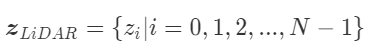
そのためにまずは、各センサ値の
頻度を集計してみます。Juliaでは、
Freqtablesというパッケージがあり、
集計結果をテーブル形式で綺麗に
まとめて出力してくれます。
Juliaコードでこのパッケージを
使うために次のコードで取り込み
ます。
using FreqTables
そして、次のようにセンサデータを
読み込んで各センサ値の頻度を集計
します。
data_path = joinpath(split(@__FILE__, "src")[1], "data/sensor_data_200.txt") df_200_mm = CSV.read(data_path, DataFrame, header=["date", "time", "ir", "lidar"], delim=' ') tbl = freqtable(df_200_mm.lidar) println("FreqTable: $(tbl)")
一番最後の行が頻度を集計する
freqtable関数で、これを実行
すると、次のような出力が得られ
ます。

左の列が集計対象の各センサ値、
右の列がそれぞれの頻度になります。
このとき、各センサ値に従って昇順に
勝手にソートしてくれるので便利です。
確率の計算
各センサ値の集計ができたので、
その結果から確率を計算してみます。
まずは次のコードで、先程の頻度
テーブルから頻度の値が入った列を
抽出します。
freqs = [value for(name, value) in enumerate(tbl)] println("Frequency: $(freqs)")
Pythonでも御馴染みのenumerate関数を
使い、リスト内包表記で頻度値の配列を
生成しています。

また、後で必要になるので、各頻度値に
対応するセンサ値も配列として用意して
おきます。
observs = [Int(obsv) for obsv in names(tbl, 1)] println("Observations: $(observs)")
先程の頻度テーブルにおける左側の列が
そうなのですが、これはこのままでは
NamedArrayという特殊な形式の配列なので、
そのままplot関数への入力として使うことが
できません。
そのため、names関数でまずはString配列
として取り出し、それをさらにInt関数で
整数配列にしています。

NamedArrayの扱い方については
こちらを参照ください。
github.com
そして、次のコードで各頻度値を
全データ数で割ることで、各センサ値の
発生確率を計算できます。
probs = freqs ./ length(df_200_mm.lidar) println("Probability: $(probs)")

最後に、計算した確率を次のコードで
可視化してみます。
bar(probs, xticks=observs, label="prob dist")
Plotsパッケージに含まれるbar関数に、
入力として計算した確率値の配列を、
xticks引数で各センサ値に合わせて
x軸を刻むように指定します。

このように、前回の記事で描いた
ヒストグラムと似たグラフが描けますが、
縦軸は頻度ではなく確率になっている
ことが分かります。
確率質量関数
上記の確率は、個別の確率を
与える関数全体を描いたものであり、
確率質量関数といいます。
各変数に対して確率がどう分布するか
を表す実体がと考えることも
でき、確率分布と呼ばれます。
確率モデル
今度は、ここまでに求めてきたセンサ値の
分布をモデル化してみます。これにより、
実際のセンサデータが無くても、センサ値
の発生をシミュレーションできるように
なります。
ガウス分布の当てはめ
先に示したようなセンサ値の頻度や確率の
分布からして、これはガウス分布に従って
いると考えられます。
ガウス分布の確率密度関数は次式のように
なり、

前回の記事で計算したセンサ値の分散を
に、平均値を
に代入することで、
特定のセンサ値が得られる確率を計算
できます。これをJuliaコードで実装すると
次のようになります。
function p(z, mu=209.7, dev=23.4) return exp(-(z - mu)^2 / (2 * dev)) / sqrt(2 * pi * dev) end
実際に得られるセンサ値の範囲が190~230と
して、上式を次のコードで描画してみましょう。
zs = Array(190:230) ys = [p(z) for z in zs] plot(zs, ys, label="gaussian distribution")
このようなグラフが描画されるはずです。

すでに作成したヒストグラムと似た形状に
なっていることが分かります。
続いて、先程の確率密度関数を
積分し、センサ値が整数に限定
される離散的な確率分布を作って
みます。
各センサ値を区間
]
の範囲で積分するとし、コードは
次のようになります。
function prob(z, width=0.5) return width * (p(z - width) + p(z + width)) end zs = Array(193:229) ys = [prob(z) for z in zs] bar(ys, xticks=zs, color=:red, alpha=0.3, label="Model") bar!(probs, xticks=observs, color=:blue, alpha=0.3, label="Observations")
このコードでは、確率密度関数の
積分から求めた確率分布と、先に
センサ値の頻度から求めた確率分布
を重ね合わせた棒グラフを描画します。

赤が積分から求めた確率分布で、
青がセンサ値の頻度から求めた
確率分布ですが、ちゃんと実際の
センサ値の傾向に近い形状でモデル化
できている事が分かります。
確率密度関数
先に示したコードではガウス分布の
確率密度関数の数式を自前で実装
しましたが、Distributionパッケージで
用意されているpdf関数を使えば、次の
ようにより簡単なコードで実現できます。
using Plots, Distributions pyplot() norm_dist = Normal(209.7, 4.84) # mu, std_dev zs = Array(193:229) ys = [pdf(norm_dist, z) for z in zs] plot(zs, ys, label="PDF")
まずこのコードの4行目では、Normal関数を
使って正規分布オブジェクトを生成して
います。第一引数が平均値、第2引数が標準
偏差です。
続いて6行目で193から229までの疑似的な
センサ値配列を定義、これを7行目でpdf関数
に入力して確率分布を計算しています。
pdf関数は確率密度関数であり、第一引数には
4行目で生成したような分布オブジェクト、
第二引数には今回のセンサ値のような変数に
あたるデータを与えます。
このコードにより、先程のグラフと同じ形状の
ものが描画されるはずです。

累積分布関数
こういった確率密度分布は積分すると
1になるわけですが、その傾向がより
分かりやすい累積分布関数というもの
もあります。

これは、変数が
以下となる確率
を
全て足し合わせたものであり、これを
全センサ値に対して計算すると、次の
ようなグラフを描画できます。
norm_dist = Normal(209.7, 4.84) # mu, std_dev zs = Array(193:229) ys = [cdf(norm_dist, z) for z in zs] plot(zs, ys, color=:red, label="CDF")

先に示した確率密度関数のコードと同様に、
まずは1行目で正規分布オブジェクトを
生成し、それをcdf関数の引数として与える
ことで累積分布関数を計算します。
グラフを見ると、各センサ値における確率
が計算されながら積算され、最終的には
1になるのが分かります。
期待値
期待値とは、ある分布について
を
無限に繰り返した場合に、の平均値がどの程度に
なるかを示すものです。
このが離散的な場合は、

連続的な場合は、

という数式で表されます。
例えば、6面のサイコロを10000回振って
出る値の平均をとることで期待値を近似的に
求めることができます。そのときのJulia
コードは次のようになります。
samples = rand(1:6, 10000) exp_value = sum(samples) / length(samples) println("Random sampling 10000 times with 6 sided dice") println("Expected value = $(exp_value)")
1行目で1~6の範囲で乱数を10000個生成
し、その平均を2行目で計算しています。
これを実行すると、次のような出力が
得られます。

まとめ
今回の記事では、センサ値の確率分布を
計算するJuliaコードを紹介しました。
扱ったのは主に正規分布でしたが、
実際はもっと複雑な形状の分布と
なるセンサ値が得られるような状況も
多くあり、それらをモデル化するには
またいろいろな前処理のテクニックが
必要になります。
次回は、そういった複雑な分布の
モデル化について紹介していきます。